NEWSページで告知を行いましたが、美術家の中村ケンゴさんが2012年に企画した二つのシンポジウム「20世紀末・日本の美術―それぞれの作家の視点から」の書籍化(発行:アートダイバー)が決定しました。第1回(2012年2月)のMEGUMI OGITA GALLERYで開催された際は、記録係をかって出ながらひどい写真を「撮りました!」とケンゴさんに渡して逆にご迷惑をおかけした思い出がありますが、その後(そのひどい写真をケンゴさんが修正してくださった写真が載っている)記録サイト( http://jart-end20.jugem.jp/?eid=1 )のためのテープ起こしなどで関わりつつ、書籍化にあたっては、ひとつ文章を書かせていただくことになりました。
自虐はそれほどにしまして…、シンポジウムは「20世紀末・日本の美術」と題して主に3人の作家の視点を通して1989年からの20世紀末を回顧されていましたが、1989年は昭和天皇が崩御し、和暦「平成」が始まった年です。ですので私はテキストで、このシンポジウムで扱われた時代を「20世紀末」ではなく、「平成」というドメスティックな和暦で顧みる、ということをしたいと思っています。昭和57年=1982年12月に群馬県で生まれた私は、この1990年代、「美術に興味があって東京にはよく出てくるよ」ということは決してなく、ただただ群馬で毎週月曜日の『週刊少年ジャンプ』発売を楽しみに学生生活を送っていました。その後大学進学で東京に出て、学生生活を送り、現在のように美術に関わる仕事をするとは、夢にも思っていない、1990年代はそういう時期です(もっと言うと、ノストラダムスで世界は終わるから勉強する必要はないと、高校時代思っていました)。僕は浪人しているので、東京に出てきたのは、平成13年=2001年9月11日の同時多発テロがあった翌年=2002年のことでした。また、大学では日本近代美術を専攻しており、現代美術を積極的に見るようになったのは、平成18=2006年頃からのことです。つまり、このシンポジウムで話されていることのほとんどは、「生きている時代としては重なっているけれども、目撃していない」ということになります。そんな自分に何ができるのでしょうか?
しかし、美術史研究は、「目撃していない」から「書けない」というものではありません。そうであったら、近代以前の美術史研究は誰もできないということになります。むしろ、だからこそ書くことができることもあるでしょう。それはもしかしたら、当時活動していた当人からしたら、正しくないこともあるかもしれない。それでも、各種資料から調査しつつ、目撃していないということを自戒しながら、書くことができることがあるのではないか。そう思いながら、今は資料をとにかく集めています。当時研究に使うともわからず、所々で同時代の批評系のの単行本や美術雑誌を買っていた過去の自分に少し感謝しながら…。
シンポジウムは、「現場の当事者」ではない私からして、とても勉強になるものでした。そして、「ここから研究を始めたい」と思いました。それまではあまりに時代が近すぎ、まとまっておりもせず、とっかかりがなかったのです。だから、ケンゴさんからこういうシンポジウムをやろうと思っていると聞いたとき、それは聞かなければならないという切実さがあったのでしょう。今回、こういったひとつの「まとまり」を与えられることで、私個人としては大きく前進しました。関係者ですので手前味噌のようになりますが、『20世紀末・日本の美術』が、そういう私と同じ立場の多くの人の、この時代=「日本・平成・美術」を研究するための、ひとつのきっかけになるのではないかと思っています。ぜひご注目いただき、できましたら予約などもしていただけると、とてもありがたいです。原稿頑もりもり張ります。
ご予約はこちらから!
http://artdiver.moo.jp/?p=628
自虐はそれほどにしまして…、シンポジウムは「20世紀末・日本の美術」と題して主に3人の作家の視点を通して1989年からの20世紀末を回顧されていましたが、1989年は昭和天皇が崩御し、和暦「平成」が始まった年です。ですので私はテキストで、このシンポジウムで扱われた時代を「20世紀末」ではなく、「平成」というドメスティックな和暦で顧みる、ということをしたいと思っています。昭和57年=1982年12月に群馬県で生まれた私は、この1990年代、「美術に興味があって東京にはよく出てくるよ」ということは決してなく、ただただ群馬で毎週月曜日の『週刊少年ジャンプ』発売を楽しみに学生生活を送っていました。その後大学進学で東京に出て、学生生活を送り、現在のように美術に関わる仕事をするとは、夢にも思っていない、1990年代はそういう時期です(もっと言うと、ノストラダムスで世界は終わるから勉強する必要はないと、高校時代思っていました)。僕は浪人しているので、東京に出てきたのは、平成13年=2001年9月11日の同時多発テロがあった翌年=2002年のことでした。また、大学では日本近代美術を専攻しており、現代美術を積極的に見るようになったのは、平成18=2006年頃からのことです。つまり、このシンポジウムで話されていることのほとんどは、「生きている時代としては重なっているけれども、目撃していない」ということになります。そんな自分に何ができるのでしょうか?
しかし、美術史研究は、「目撃していない」から「書けない」というものではありません。そうであったら、近代以前の美術史研究は誰もできないということになります。むしろ、だからこそ書くことができることもあるでしょう。それはもしかしたら、当時活動していた当人からしたら、正しくないこともあるかもしれない。それでも、各種資料から調査しつつ、目撃していないということを自戒しながら、書くことができることがあるのではないか。そう思いながら、今は資料をとにかく集めています。当時研究に使うともわからず、所々で同時代の批評系のの単行本や美術雑誌を買っていた過去の自分に少し感謝しながら…。
シンポジウムは、「現場の当事者」ではない私からして、とても勉強になるものでした。そして、「ここから研究を始めたい」と思いました。それまではあまりに時代が近すぎ、まとまっておりもせず、とっかかりがなかったのです。だから、ケンゴさんからこういうシンポジウムをやろうと思っていると聞いたとき、それは聞かなければならないという切実さがあったのでしょう。今回、こういったひとつの「まとまり」を与えられることで、私個人としては大きく前進しました。関係者ですので手前味噌のようになりますが、『20世紀末・日本の美術』が、そういう私と同じ立場の多くの人の、この時代=「日本・平成・美術」を研究するための、ひとつのきっかけになるのではないかと思っています。ぜひご注目いただき、できましたら予約などもしていただけると、とてもありがたいです。原稿頑もりもり張ります。
ご予約はこちらから!
http://artdiver.moo.jp/?p=628
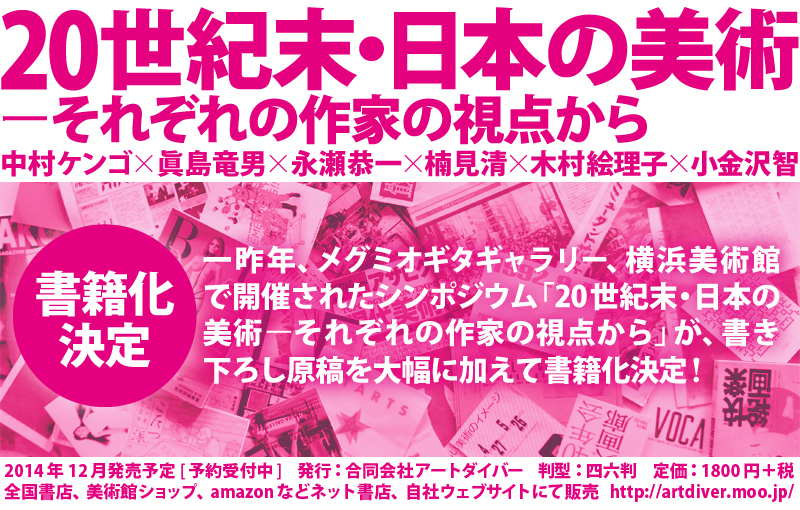
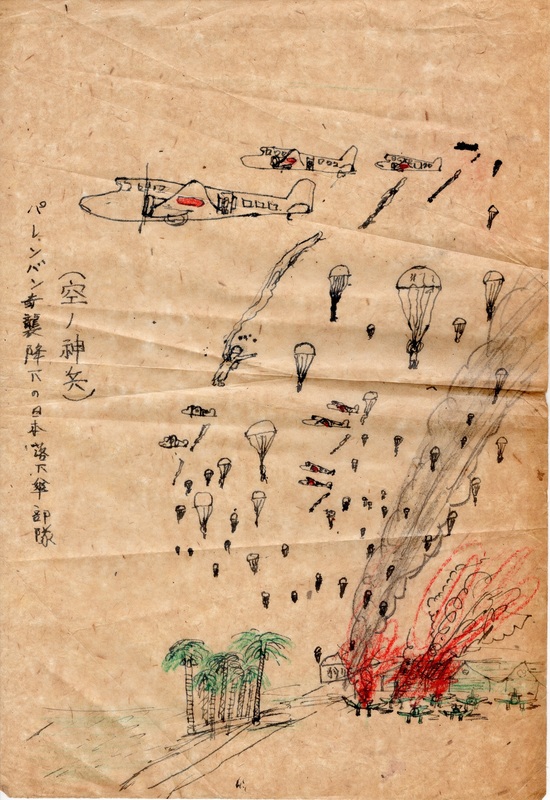
 RSS Feed
RSS Feed