毎日は無理でも数日くらいおきに更新したいと思っていたブログもいつの間にか滞ってしまっていました。むむむむむ。
以下、いくつかのこと。
1
年中、日本各地で行きたいなと思う展覧会が沢山行われていて、遠方の場合は頭を悩ませているのですが、今月は関東以外で3箇所行くことができました(静岡、京都・兵庫、福島)。以下は(列挙するには数多い)ギャラリーをのぞいての美術館で拝見した展覧会です。
・静岡県立美術館「美少女の美術史」展
・京都国立博物館「国宝 鳥獣戯画と高山寺」展
・芦屋市立美術博物館「art trip vol.01窓の外、恋の旅。/風景と表現」展
・喜多方市美術館「セピロマの夢、「ピ」はピカソの「ピ」展
いずれもとても面白く、常設展もあるところは拝見して(京博のリニューアルすごいですね)、各感想をしっかり書きたいところなのですが、時間がなくかないません...。ともあれ、芦屋市立美術博物館の展覧会のみ、現時点でも開催中なので、ぜひお近くの方も遠方の方も、閉幕直前ですがおすすめさせてください。コレクションをどういう文脈や切り口で展示するのか、というのは、近年の美術館の大きな課題だと思いますが、コレクションに、招聘した現代作家の作品を加えて構成した同展は、とても楽しく、心あざやかな思いのする展覧会でした。素晴らしかったです。11月30日(日)まで開催されています。
芦屋市立美術博物館「art trip vol.01窓の外、恋の旅。/風景と表現」展
http://ashiya-museum.jp/exhibition_new
2
静岡と京都・兵庫は個人的に行ったものですが、福島県の喜多方は、呼んでいただいてうかがったものでした。妖怪や神仏など目に見えないものを絵画化されている作家の金子富之さんが、喜多方でのリサーチを重ね、その成果を展覧会で発表する「森のはこ舟アートプロジェクト」の一環で、12月23日(火)に対談をさせていただくことになっており、その事前リサーチで呼んでいただきました。
1泊2日でうかがって、金子富之さん、そしてプログラムのご担当の方とあちらこちらへ。はじめての喜多方は、喜多方ラーメンや馬刺しそして日本酒など食べ物と飲み物のたまらない記憶を残しつつ、連れて行っていただいた不思議な場所が、あそこは一体なんだったのだ!と今なお思わせます。金子さんとの対談では、作品に加え、そういうお話をさせていただくことになるのではと思いますので、クリスマス直前でそろそろ仕事納めかという時期ではありますが、ぜひお時間ある方は喜多方までお越しください。ただのトークだけではないプログラムを金子さんが考えてらっしゃるので、とても面白くなるのではないかと思います。詳細は、webに後日アップされるかと思いますので、チェックしてみてください。
森のはこ舟アートプロジェクト
http://www.morinohakobune.jp
3
最近行ったところはそんなところで、日常生活では、先日もお知らせしました中村ケンゴさん編著『20世紀末・日本の美術ーそれぞれの作家の視点から』(アートダイバー)に書かせていただく原稿のため、20世紀末に開催された、主に日本の同時代をテーマにした展覧会図録や書籍を買い集めていました。
もちろんすべてを網羅するのは不可能なのですが、これは押さえなければならないのではないか...というものを集め、それらから導かれる「20世紀末・日本の美術の形成のされ方」についての考えを整理しながら、原稿にまとめています。『20世紀末・日本の美術ーそれぞれの作家の視点から』は、そのタイトルどおり、「それぞれの作家の視点から」語られる「20世紀末・日本の美術」です。ただそれらは主に1970年前後に生まれた方々による話なので、1982年生まれの私は直接体験していません。ですから、それらのお話はとても刺激的で勉強になるのですが、そのまま受け取ってしまってはいけないのではないか?、自分でもしっかり当時の状況を知ろうとしなければならないのでは意味がないのではないか? と思い、そうしてまとめられたものが「なかがき」として掲載される予定です。
詳しくは近刊予定の本で...と思いますが、調べていて思ったのは、20世紀末というたかだか20年くらい前のことでも調べるのは大変で、図録が顕著ですが書籍はものによっては結構なプレミアがついている、ないしは市場に出回ってすらいないものがちらほらあります(そして、美術関係の図録は専門図書館でないと中々所蔵していません)。しかし、一番怖いなと思った、それに気づけてよかったなと思ったのは、「たかだか20年前くらいのことだからと思い、なんとなくわかったような気になっている自分」にほかなりませんでした。私は、この原稿を書きながら、どれだけこの「なんとなくわかったような気になっている自分」を消したいと思ったか。それが、「過去」への認識を偏らせ、「未来」への展望を誤らせる。すなわち「今」が不安定になる(にもかかわらず、それに気づいていない!)。調べないといけないものが多々あり、本当にこればかりはきりがないですが、それでも、このことに気づいたことの収穫は、とても大きく、心底よかったと思います。本は、税別1,800円で、現在ご予約受付中です。
【予約】『20世紀末・日本の美術ーそれぞれの作家の視点から』中村ケンゴ編著
http://artdiver.moo.jp/?p=767
ということで、現在のいろいろなところへ行きつつ、図録や本によって時空を超えながら、日々を過ごしています。
以下、いくつかのこと。
1
年中、日本各地で行きたいなと思う展覧会が沢山行われていて、遠方の場合は頭を悩ませているのですが、今月は関東以外で3箇所行くことができました(静岡、京都・兵庫、福島)。以下は(列挙するには数多い)ギャラリーをのぞいての美術館で拝見した展覧会です。
・静岡県立美術館「美少女の美術史」展
・京都国立博物館「国宝 鳥獣戯画と高山寺」展
・芦屋市立美術博物館「art trip vol.01窓の外、恋の旅。/風景と表現」展
・喜多方市美術館「セピロマの夢、「ピ」はピカソの「ピ」展
いずれもとても面白く、常設展もあるところは拝見して(京博のリニューアルすごいですね)、各感想をしっかり書きたいところなのですが、時間がなくかないません...。ともあれ、芦屋市立美術博物館の展覧会のみ、現時点でも開催中なので、ぜひお近くの方も遠方の方も、閉幕直前ですがおすすめさせてください。コレクションをどういう文脈や切り口で展示するのか、というのは、近年の美術館の大きな課題だと思いますが、コレクションに、招聘した現代作家の作品を加えて構成した同展は、とても楽しく、心あざやかな思いのする展覧会でした。素晴らしかったです。11月30日(日)まで開催されています。
芦屋市立美術博物館「art trip vol.01窓の外、恋の旅。/風景と表現」展
http://ashiya-museum.jp/exhibition_new
2
静岡と京都・兵庫は個人的に行ったものですが、福島県の喜多方は、呼んでいただいてうかがったものでした。妖怪や神仏など目に見えないものを絵画化されている作家の金子富之さんが、喜多方でのリサーチを重ね、その成果を展覧会で発表する「森のはこ舟アートプロジェクト」の一環で、12月23日(火)に対談をさせていただくことになっており、その事前リサーチで呼んでいただきました。
1泊2日でうかがって、金子富之さん、そしてプログラムのご担当の方とあちらこちらへ。はじめての喜多方は、喜多方ラーメンや馬刺しそして日本酒など食べ物と飲み物のたまらない記憶を残しつつ、連れて行っていただいた不思議な場所が、あそこは一体なんだったのだ!と今なお思わせます。金子さんとの対談では、作品に加え、そういうお話をさせていただくことになるのではと思いますので、クリスマス直前でそろそろ仕事納めかという時期ではありますが、ぜひお時間ある方は喜多方までお越しください。ただのトークだけではないプログラムを金子さんが考えてらっしゃるので、とても面白くなるのではないかと思います。詳細は、webに後日アップされるかと思いますので、チェックしてみてください。
森のはこ舟アートプロジェクト
http://www.morinohakobune.jp
3
最近行ったところはそんなところで、日常生活では、先日もお知らせしました中村ケンゴさん編著『20世紀末・日本の美術ーそれぞれの作家の視点から』(アートダイバー)に書かせていただく原稿のため、20世紀末に開催された、主に日本の同時代をテーマにした展覧会図録や書籍を買い集めていました。
もちろんすべてを網羅するのは不可能なのですが、これは押さえなければならないのではないか...というものを集め、それらから導かれる「20世紀末・日本の美術の形成のされ方」についての考えを整理しながら、原稿にまとめています。『20世紀末・日本の美術ーそれぞれの作家の視点から』は、そのタイトルどおり、「それぞれの作家の視点から」語られる「20世紀末・日本の美術」です。ただそれらは主に1970年前後に生まれた方々による話なので、1982年生まれの私は直接体験していません。ですから、それらのお話はとても刺激的で勉強になるのですが、そのまま受け取ってしまってはいけないのではないか?、自分でもしっかり当時の状況を知ろうとしなければならないのでは意味がないのではないか? と思い、そうしてまとめられたものが「なかがき」として掲載される予定です。
詳しくは近刊予定の本で...と思いますが、調べていて思ったのは、20世紀末というたかだか20年くらい前のことでも調べるのは大変で、図録が顕著ですが書籍はものによっては結構なプレミアがついている、ないしは市場に出回ってすらいないものがちらほらあります(そして、美術関係の図録は専門図書館でないと中々所蔵していません)。しかし、一番怖いなと思った、それに気づけてよかったなと思ったのは、「たかだか20年前くらいのことだからと思い、なんとなくわかったような気になっている自分」にほかなりませんでした。私は、この原稿を書きながら、どれだけこの「なんとなくわかったような気になっている自分」を消したいと思ったか。それが、「過去」への認識を偏らせ、「未来」への展望を誤らせる。すなわち「今」が不安定になる(にもかかわらず、それに気づいていない!)。調べないといけないものが多々あり、本当にこればかりはきりがないですが、それでも、このことに気づいたことの収穫は、とても大きく、心底よかったと思います。本は、税別1,800円で、現在ご予約受付中です。
【予約】『20世紀末・日本の美術ーそれぞれの作家の視点から』中村ケンゴ編著
http://artdiver.moo.jp/?p=767
ということで、現在のいろいろなところへ行きつつ、図録や本によって時空を超えながら、日々を過ごしています。
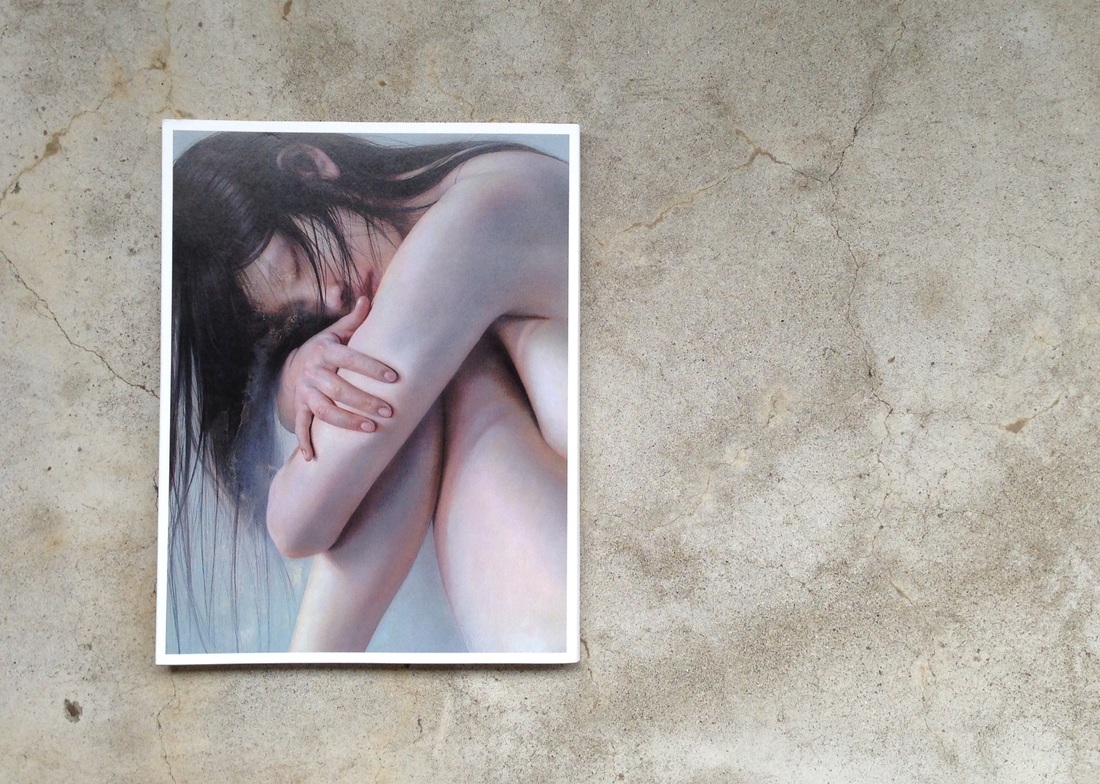



 RSS Feed
RSS Feed