12月23日(火祝)、日本画家の金子富之さん(1978年生まれ)との対談のため、喜多方へ行ってきました。「森のはこ舟アートプロジェクト」の一環として大和川酒蔵(酒蔵!)の一部を会場にして行われている個展「森と人のミステリウム(現代絵画表現から元型(古代型)への回帰)」関連イベントです。
対談の詳細は、なかなか全容を言葉にしがたいところがあるのですが、いわゆる美術関係の対談でよくある展覧会内容についての話にとどまらず、金子さんが作品を作る前提として備えている気質のようなものに触れる時間がむしろメインだったように思います。それは対談中に金子さん発案で設けられた「森への質問」といった参加者が個々で「森に何かを聞いてみる」という時間であったり、合気の実演だったりして(私は技をかけられました)、私は、金子さんによって対談の自由さを知りながら、ああこういう人だからこういう作品が生まれるのだと思いました。
金子さんの作品は、一見、おどろおどろしく、オカルティックで、時に目をそむけたくなるようなものが描かれています。そのまなざしは、妖怪であったり、精霊であったり、神仏であったり、すなわち一貫して「目に見えないもの」に向けられていますが、それらを具現化し、絵として強いものにするためのいわば「想像力」のベースに、各種文献や過去のイメージの研究による知識の蓄積があり、それが作品になによりの強度を与えているように思います。これは、私がはじめて金子さんの作品を個展で見た日本橋髙島屋美術画廊X(2011年)の際も、さらには今回の個展でも展示されているおびただしい数のアイデアノート(展示ではコピー)からもうかがえるものです。そして、とりわけ近年の作品を見ていると、金子さんの作品は、仏画や仏像等、宗教美術との関係性から、しっかり考えないといけないのだろうなと思いました。それはつまり、「不可視の神を象る」とはどういうことか、ということにほかなりません。
金子さんの個展は12月28日(日)まで開催されています。私が行ったときは前日大雪だったようでとても美しい雪景色、さらには喜多方には美味しい喜多方ラーメンや日本酒(蔵が10軒!)など楽しみどころ多数です。なかなかこの規模の個展は見られないと思いますので、お時間ある方はぜひ。
金子富之さんの展示の詳細はこちら
http://www.morinohakobune.jp/news/20141203.html
私は東京から新幹線を使いましたが、バスだと安い&直通もあって行きやすそうです
http://time.jrbuskanto.co.jp/bk020060.html
対談の詳細は、なかなか全容を言葉にしがたいところがあるのですが、いわゆる美術関係の対談でよくある展覧会内容についての話にとどまらず、金子さんが作品を作る前提として備えている気質のようなものに触れる時間がむしろメインだったように思います。それは対談中に金子さん発案で設けられた「森への質問」といった参加者が個々で「森に何かを聞いてみる」という時間であったり、合気の実演だったりして(私は技をかけられました)、私は、金子さんによって対談の自由さを知りながら、ああこういう人だからこういう作品が生まれるのだと思いました。
金子さんの作品は、一見、おどろおどろしく、オカルティックで、時に目をそむけたくなるようなものが描かれています。そのまなざしは、妖怪であったり、精霊であったり、神仏であったり、すなわち一貫して「目に見えないもの」に向けられていますが、それらを具現化し、絵として強いものにするためのいわば「想像力」のベースに、各種文献や過去のイメージの研究による知識の蓄積があり、それが作品になによりの強度を与えているように思います。これは、私がはじめて金子さんの作品を個展で見た日本橋髙島屋美術画廊X(2011年)の際も、さらには今回の個展でも展示されているおびただしい数のアイデアノート(展示ではコピー)からもうかがえるものです。そして、とりわけ近年の作品を見ていると、金子さんの作品は、仏画や仏像等、宗教美術との関係性から、しっかり考えないといけないのだろうなと思いました。それはつまり、「不可視の神を象る」とはどういうことか、ということにほかなりません。
金子さんの個展は12月28日(日)まで開催されています。私が行ったときは前日大雪だったようでとても美しい雪景色、さらには喜多方には美味しい喜多方ラーメンや日本酒(蔵が10軒!)など楽しみどころ多数です。なかなかこの規模の個展は見られないと思いますので、お時間ある方はぜひ。
金子富之さんの展示の詳細はこちら
http://www.morinohakobune.jp/news/20141203.html
私は東京から新幹線を使いましたが、バスだと安い&直通もあって行きやすそうです
http://time.jrbuskanto.co.jp/bk020060.html

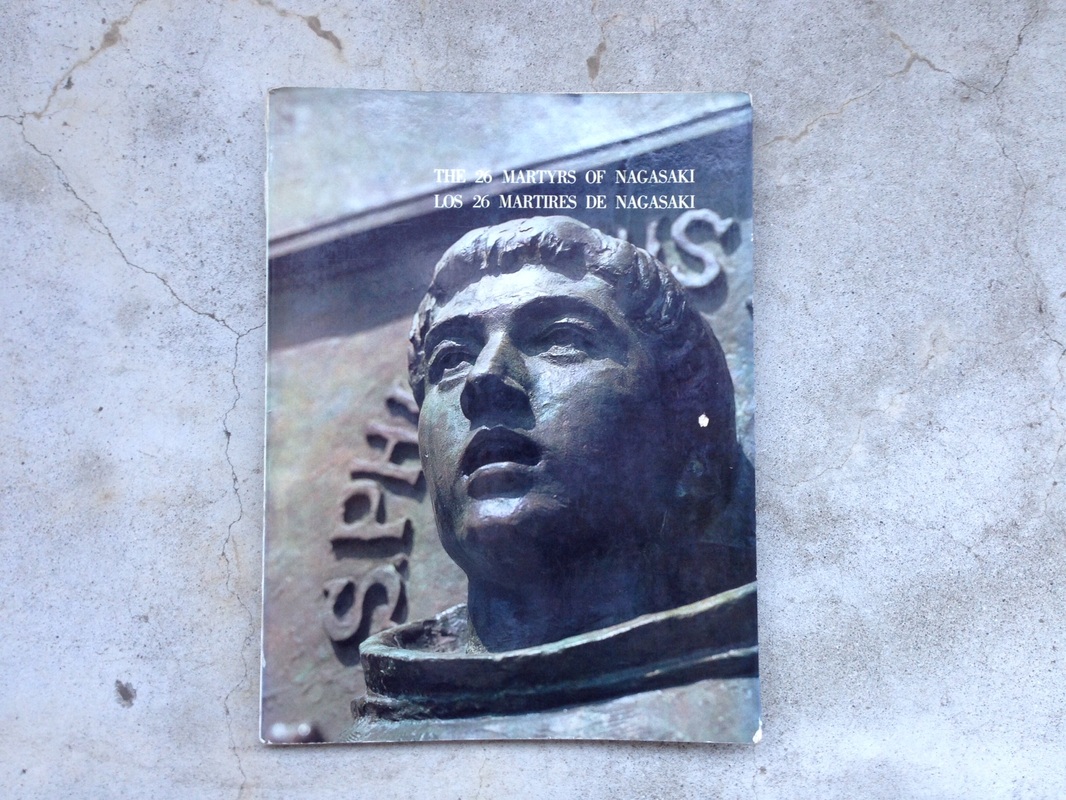
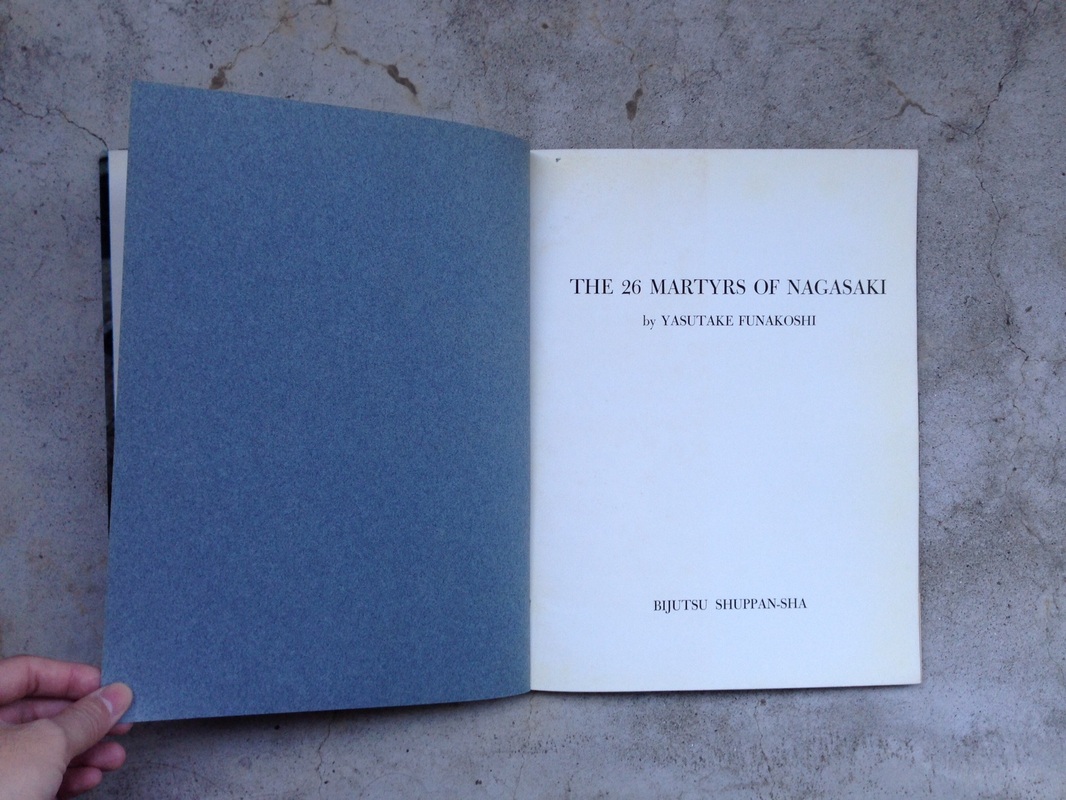
 RSS Feed
RSS Feed