2015年、早くも8月ですね。
4月に美術館を退職してからいわゆる定職についていない自分は、当初、どこかふわふわとしていて足元がおぼつかない感じがあり、自分で足元を、背筋を、しっかりとしなければどこにも立つことができないと改めて気づくことからこの春をはじめました。
その間、近づいた人もいれば、遠のいた人もいて、それは環境のせいでもあり、自らのせいでもあり、その中で「あなたは誰か?」と、人からも尋ねられ、また、なによりそう自問する毎日であったような気がします。いつも違うことを言っているような思いがぬぐえ切れず、明確に答えは出ませんが、それはそもそも出ないものなのかもしれないと最近は考えはじめています。その中でもこの感情や体が何かに触れて動くということだけが大事なのではないかと。
無料で使っていたこのweeblyのサービスでしたが、やっとドメインを取得しました。
http://www.koganezawasatoshi.com/
暑くてクラクラする毎日で、ひとつでもすっきりした夏のはじまりです。
4月に美術館を退職してからいわゆる定職についていない自分は、当初、どこかふわふわとしていて足元がおぼつかない感じがあり、自分で足元を、背筋を、しっかりとしなければどこにも立つことができないと改めて気づくことからこの春をはじめました。
その間、近づいた人もいれば、遠のいた人もいて、それは環境のせいでもあり、自らのせいでもあり、その中で「あなたは誰か?」と、人からも尋ねられ、また、なによりそう自問する毎日であったような気がします。いつも違うことを言っているような思いがぬぐえ切れず、明確に答えは出ませんが、それはそもそも出ないものなのかもしれないと最近は考えはじめています。その中でもこの感情や体が何かに触れて動くということだけが大事なのではないかと。
無料で使っていたこのweeblyのサービスでしたが、やっとドメインを取得しました。
http://www.koganezawasatoshi.com/
暑くてクラクラする毎日で、ひとつでもすっきりした夏のはじまりです。
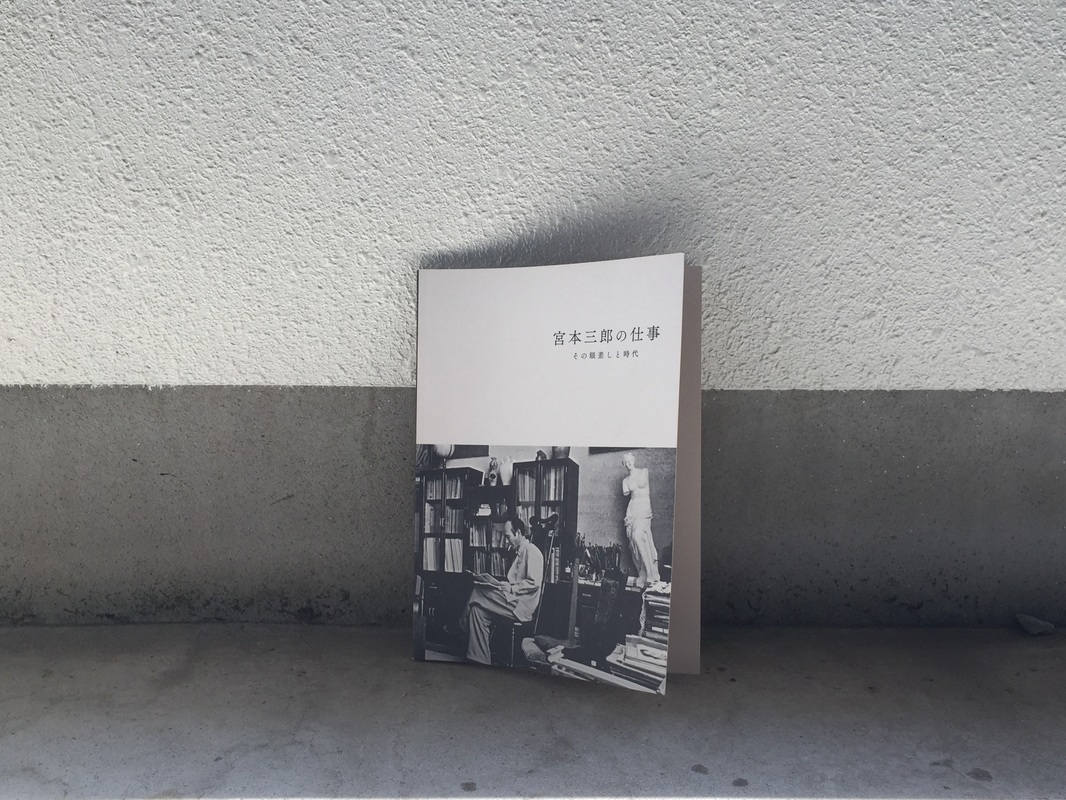


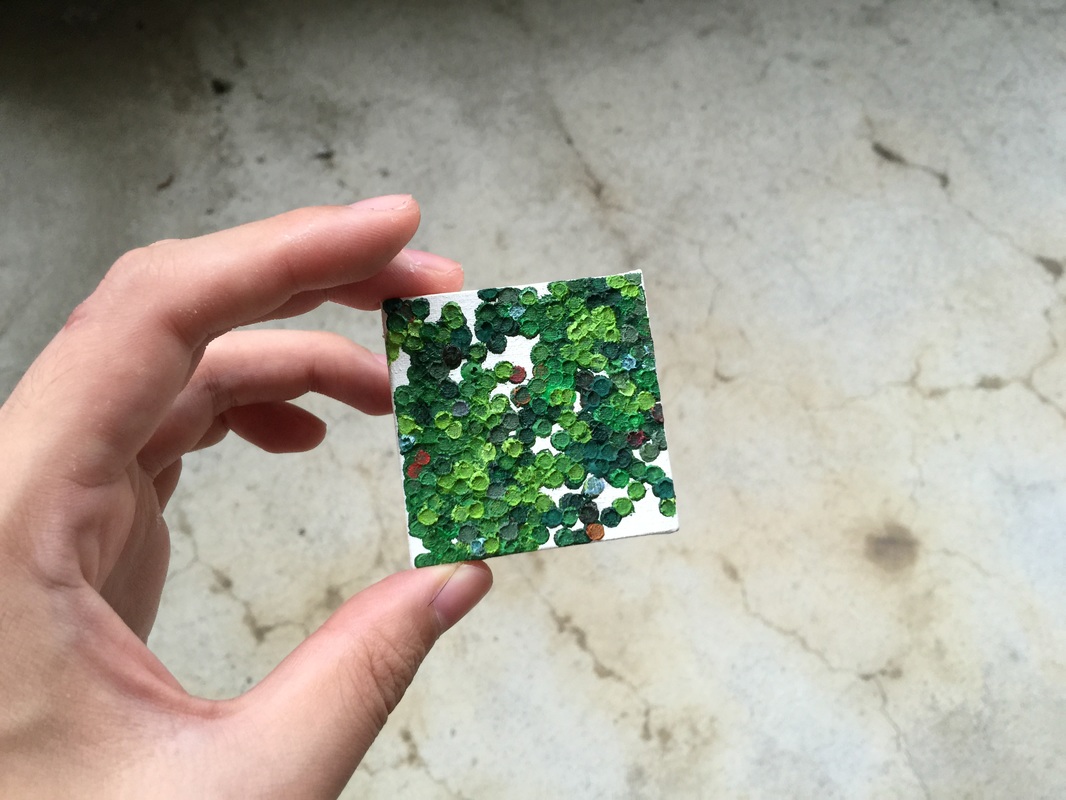
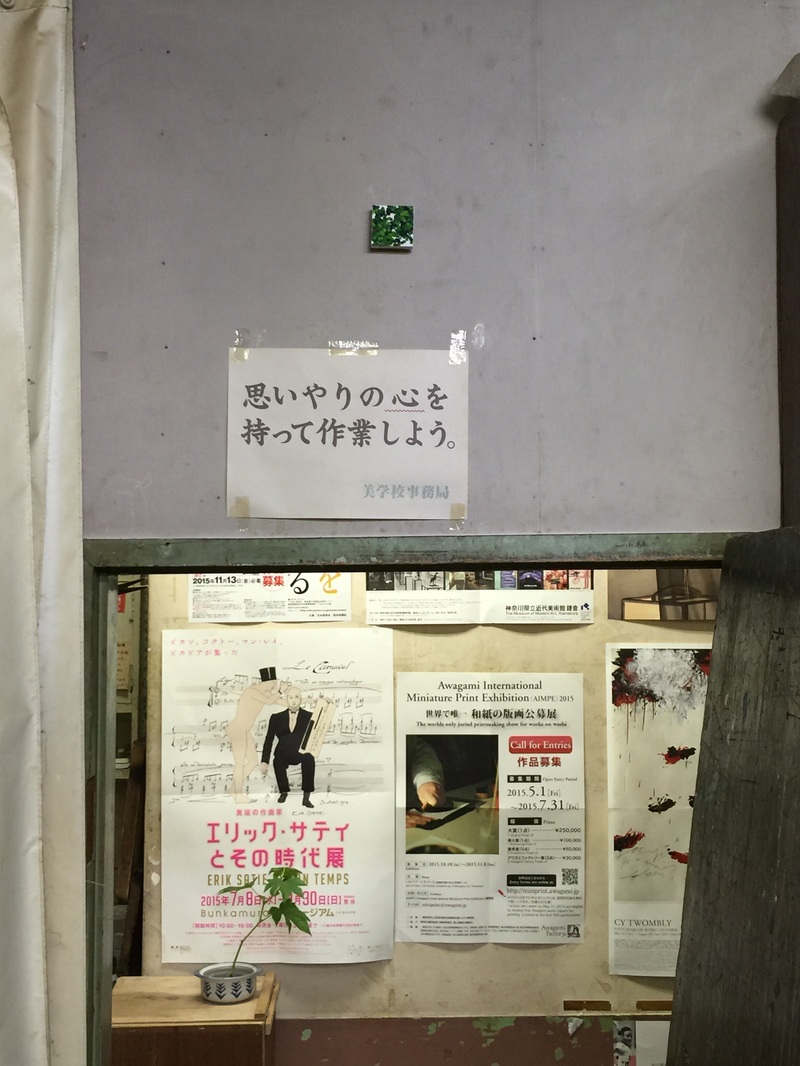
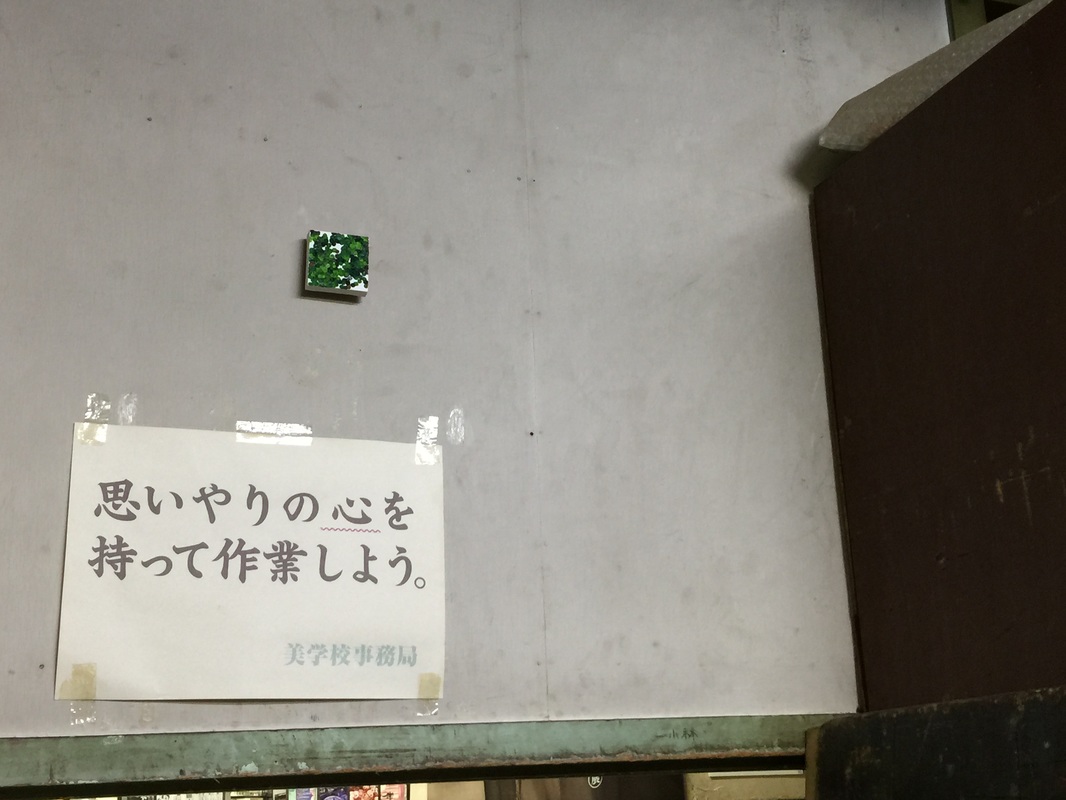
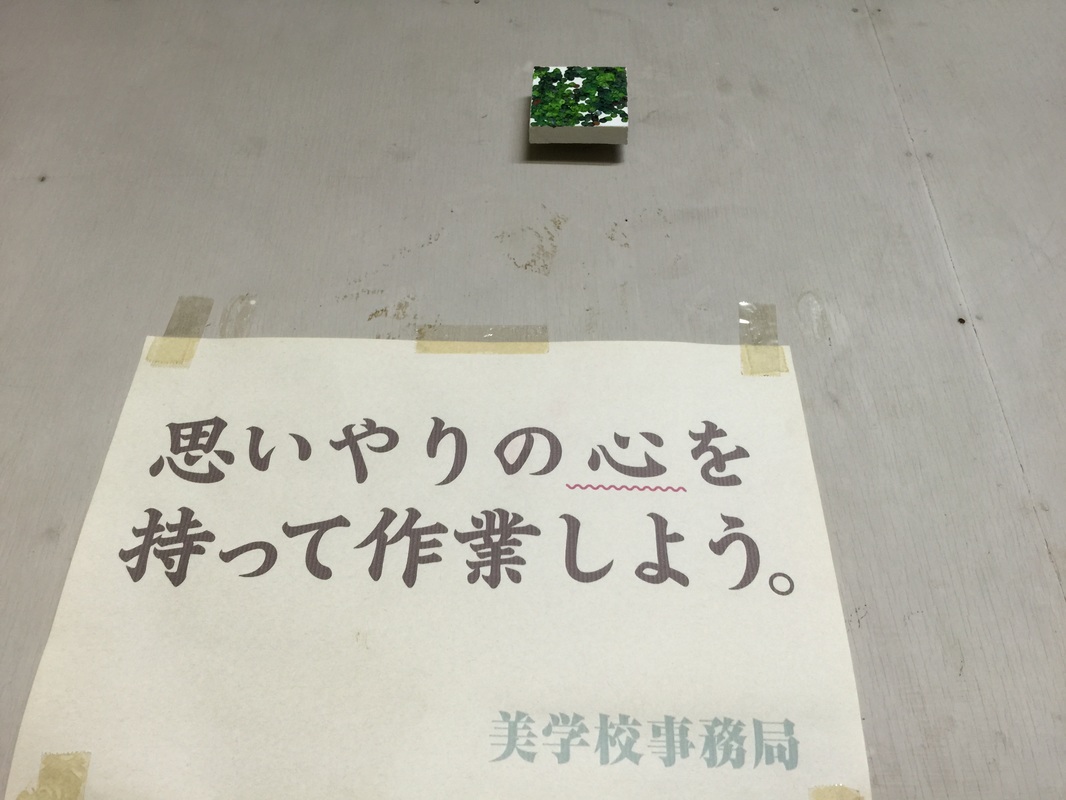
 RSS Feed
RSS Feed