美術の研究や批評というものがあって、私はその範疇で仕事をしていると自覚しているけれど、そういう範疇で具体的かつ理路整然に語ることが難しいものがある、というか、ただ今の自分のできること・できないことの範囲を考えたとき、自分にとっての言葉というものがどれだけ正確に自分の感情を伝えることができるのだろうか、ということに対する疑義を、作家というよりもその彼や彼女が作り上げた作品を前にして感じることがある。彼にかぎらないことではあるけれど、松岡亮さんの作品を前にとりわけそれを感じるのはなぜだろう。なぜだろう、と思いながら、それの答えはいくら作品を見ても本人と話をしてもわからず、しばらくして、わかるとか・わからないということが些末なものなのかもしれない、ということに気づく状況にたどり着く。これはなんだろう、と何度も考える。
絵は、というときの絵自体が、さまざまなフィルターをかけられていて、それは歴史や理論や風土やジェンダーなどさまざまなものが描画材料によるイメージや、イメージならざるものに覆いかぶさっているのだけれど(そういう言葉自体にも、語る主体の個々の無数のフィルターがある)、したがってもはやなにがなんだか一言ではとても言いにくい、と私自身は思っていて、しかし、そのなかでなにか自分にとって響くものがあり、そういう心境のなかでも松岡亮さんの絵は、ただ絵としてそこにある、と私は今言うのだけれど、そのただ絵としてそこにあるということの具体的な説明をできるわけではない私の言葉の弱さがここにある。けれど好きなのだ。
これはなんだろう、と繰り返したい。この、好きだとは、なんなのだろう。その根本には、「美しさ」がある。
なにかに対する「美しさ」の説明を実感ともなって具体的にすることが難しいことと同様に(実際美とはひとつのイデオロギーである)、個々の感情の起伏や表出は個々の経験や環境によって出方が異なるものだから、容易に定義づけられるものではない、という当たり前のことに対する気づきがまずあり、そこからどれだけの言葉を積んでいくことができるのか(自分ではない誰か=あなたに対して)、それによって自分はなにを言うことができることだろうか。
そういう意味では、まったく、この文章自体はまだどこにも今のところたどり着いていない。書けばどこかにたどり着くことができるのかもしれないと思いながら、有楽町と原宿の松岡さんのそれぞれ尋ねるのは二度目の今回の各個展の帰り道、書きはじめたけれど、まだ最初のところでぐるぐる回っているような感触がある。感触というか事実そうだ。言い切っていないことの弱さを、ここで今私は気づかなければならないのだ。言い切れと、松岡亮さんの絵は私に言う。美術のことも、そうではないことも。 おそらくそれは、生きることに対してのあたなの感情に対してだ。
しかし、とはいえ、その最初のところでぐるぐる回らせてくれる作品や作家と出会ったことがありがたいと思う。これは、これまで松岡さんだけではない、(雑な言い方になるけれども)古今東西の作家や作品との出会いがあり、そうして、今の個人的なタイミングでは松岡さんの絵が響いたということだ。
そうして、個人的に説明不可能なもの、言語化不可能なものに出会ったとき、これまで自分は絵を、美術を見てきてよかったと思う。これまでのすべての美術と、今と、これからの未知のすべての存在が、体験も予感も含めて、ブワッと立ち上がるような心地がして、まったく抽象的な言い方だけれども、そう、そうして私は今、自分の見てきた美術の総体のただ中にいる。
そうではないか? 鑑賞とは、最終的にはそういう個人的なものだ(美術は、必ずしも個人的なものではないけれども、最後には個人的なものであると信じたい)。かつ、それは今見ている絵が呼び起こしたもので、さらにこれから見る絵が呼び起こしたものであるかもしれない。 という意味では、私は絵の鑑賞の過去と現在のただ中にいて、未来にもいる。鑑賞というものを、広く考えたい。それは生きることと密接に結びついたものだ。絵や、美術は、生きることとは関係がないだなんて、なんてつまらない言葉だろう。
絵だけが今の自分を作っているわけではもちろんない。いろいろなものが、本当にいろいろなものや人が、これまでの自分を作り、これからも作るだろう。けれどもそのなかでも美術は、自分にとっては自分を形作る大事なもののひとつになっていて、そのことを誰にも強制しようとは思わないけれど、それを大事に思う人が私以外にも、実際私以上にいるだろうから、今後それに対して応えられる仕事を私はただ個人として続けていきたい。
間もなく終わってしまう、松岡亮さんの個展をぜひ見てください。
◉松岡亮個展「実と花 時と間 葉と月」
2015年8月1日(土)〜8月31日(月) 12時〜20時
定休日: 水曜日
BLOCK HOUSE
東京都渋谷区神宮前 6-12-9(地下 1 階ギャラリースペース・3 階カフェバー・4 階ギャラリー)
Website:http://blockhouse.jp
代表: 小野寺宏至
◉あそびとまなびの種展
2015年7月14日(火)〜8月29日(土)10時〜21時
定休日:会期中無休
無印良品 ATELIER MUJI
東京都千代田区丸の内3−8−3 インフォス有楽町 2F
Website:http://www.muji.net/lab/ateliermuji
絵は、というときの絵自体が、さまざまなフィルターをかけられていて、それは歴史や理論や風土やジェンダーなどさまざまなものが描画材料によるイメージや、イメージならざるものに覆いかぶさっているのだけれど(そういう言葉自体にも、語る主体の個々の無数のフィルターがある)、したがってもはやなにがなんだか一言ではとても言いにくい、と私自身は思っていて、しかし、そのなかでなにか自分にとって響くものがあり、そういう心境のなかでも松岡亮さんの絵は、ただ絵としてそこにある、と私は今言うのだけれど、そのただ絵としてそこにあるということの具体的な説明をできるわけではない私の言葉の弱さがここにある。けれど好きなのだ。
これはなんだろう、と繰り返したい。この、好きだとは、なんなのだろう。その根本には、「美しさ」がある。
なにかに対する「美しさ」の説明を実感ともなって具体的にすることが難しいことと同様に(実際美とはひとつのイデオロギーである)、個々の感情の起伏や表出は個々の経験や環境によって出方が異なるものだから、容易に定義づけられるものではない、という当たり前のことに対する気づきがまずあり、そこからどれだけの言葉を積んでいくことができるのか(自分ではない誰か=あなたに対して)、それによって自分はなにを言うことができることだろうか。
そういう意味では、まったく、この文章自体はまだどこにも今のところたどり着いていない。書けばどこかにたどり着くことができるのかもしれないと思いながら、有楽町と原宿の松岡さんのそれぞれ尋ねるのは二度目の今回の各個展の帰り道、書きはじめたけれど、まだ最初のところでぐるぐる回っているような感触がある。感触というか事実そうだ。言い切っていないことの弱さを、ここで今私は気づかなければならないのだ。言い切れと、松岡亮さんの絵は私に言う。美術のことも、そうではないことも。 おそらくそれは、生きることに対してのあたなの感情に対してだ。
しかし、とはいえ、その最初のところでぐるぐる回らせてくれる作品や作家と出会ったことがありがたいと思う。これは、これまで松岡さんだけではない、(雑な言い方になるけれども)古今東西の作家や作品との出会いがあり、そうして、今の個人的なタイミングでは松岡さんの絵が響いたということだ。
そうして、個人的に説明不可能なもの、言語化不可能なものに出会ったとき、これまで自分は絵を、美術を見てきてよかったと思う。これまでのすべての美術と、今と、これからの未知のすべての存在が、体験も予感も含めて、ブワッと立ち上がるような心地がして、まったく抽象的な言い方だけれども、そう、そうして私は今、自分の見てきた美術の総体のただ中にいる。
そうではないか? 鑑賞とは、最終的にはそういう個人的なものだ(美術は、必ずしも個人的なものではないけれども、最後には個人的なものであると信じたい)。かつ、それは今見ている絵が呼び起こしたもので、さらにこれから見る絵が呼び起こしたものであるかもしれない。 という意味では、私は絵の鑑賞の過去と現在のただ中にいて、未来にもいる。鑑賞というものを、広く考えたい。それは生きることと密接に結びついたものだ。絵や、美術は、生きることとは関係がないだなんて、なんてつまらない言葉だろう。
絵だけが今の自分を作っているわけではもちろんない。いろいろなものが、本当にいろいろなものや人が、これまでの自分を作り、これからも作るだろう。けれどもそのなかでも美術は、自分にとっては自分を形作る大事なもののひとつになっていて、そのことを誰にも強制しようとは思わないけれど、それを大事に思う人が私以外にも、実際私以上にいるだろうから、今後それに対して応えられる仕事を私はただ個人として続けていきたい。
間もなく終わってしまう、松岡亮さんの個展をぜひ見てください。
◉松岡亮個展「実と花 時と間 葉と月」
2015年8月1日(土)〜8月31日(月) 12時〜20時
定休日: 水曜日
BLOCK HOUSE
東京都渋谷区神宮前 6-12-9(地下 1 階ギャラリースペース・3 階カフェバー・4 階ギャラリー)
Website:http://blockhouse.jp
代表: 小野寺宏至
◉あそびとまなびの種展
2015年7月14日(火)〜8月29日(土)10時〜21時
定休日:会期中無休
無印良品 ATELIER MUJI
東京都千代田区丸の内3−8−3 インフォス有楽町 2F
Website:http://www.muji.net/lab/ateliermuji






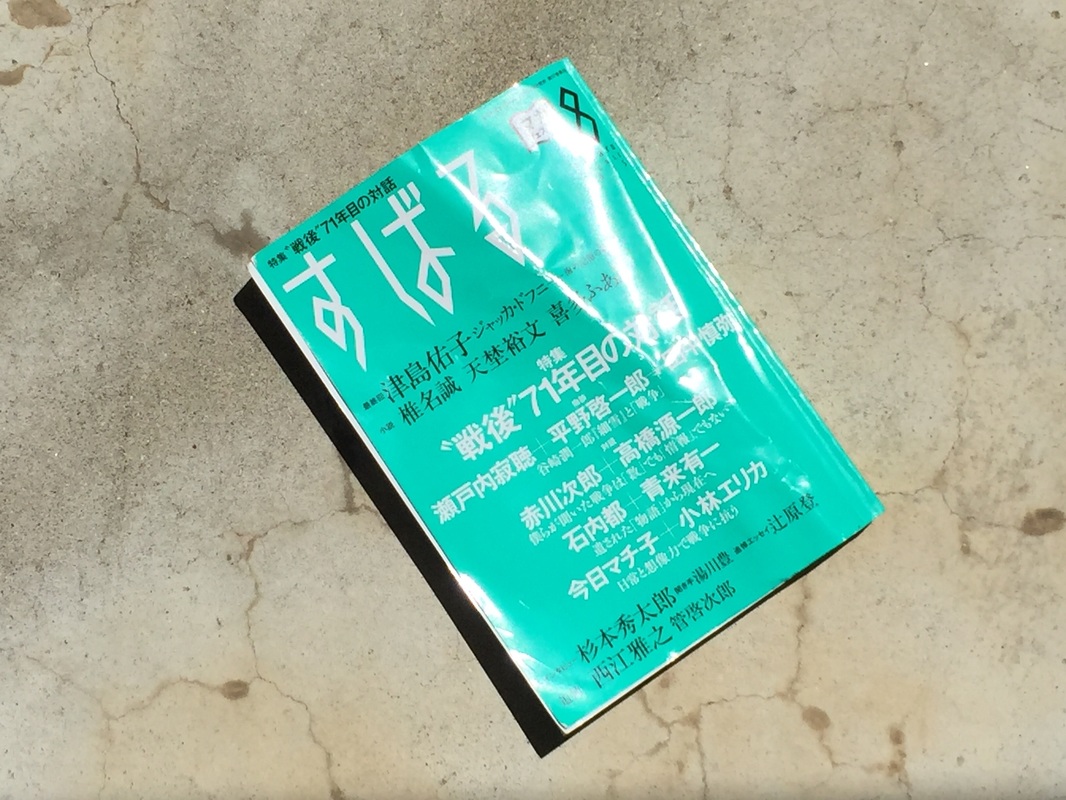
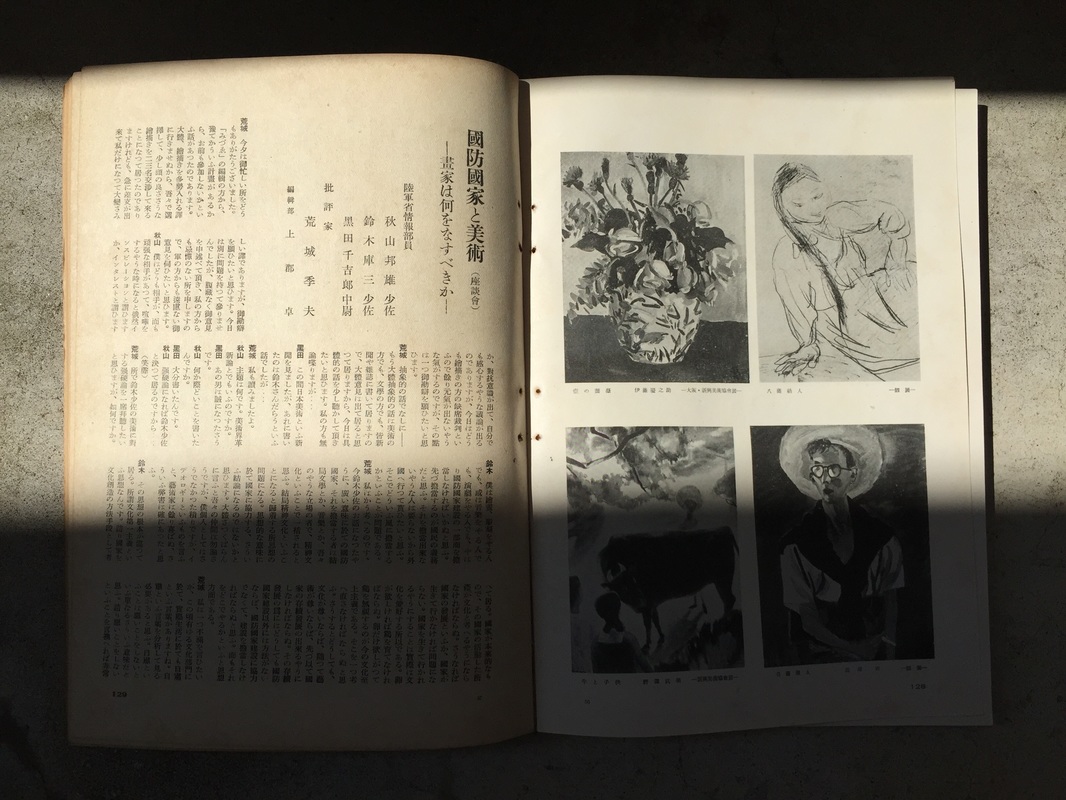
 RSS Feed
RSS Feed